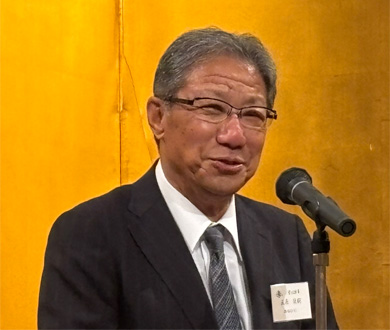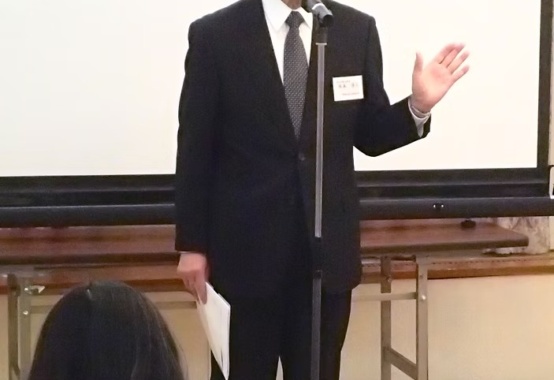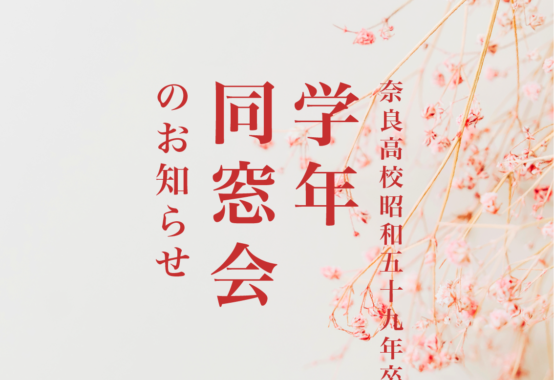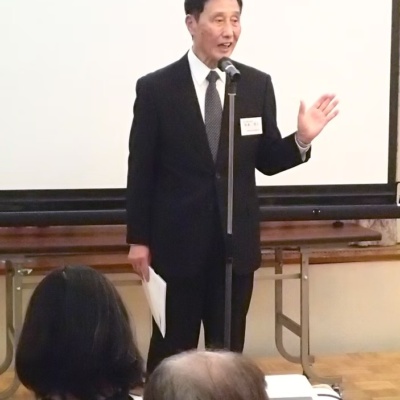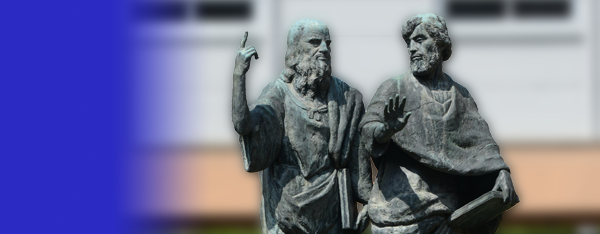宝相華会会長に就任して
萩原俊嗣(昭和48年卒)
令和7年4月の宝相華会総会にて瀬川雅数会長の後任として承認され、12代目の会長として就任しました。歴代の会長には錚々たる方々が就任されており、浅学菲才、人脈にも乏しい私には結構荷が重い役職でありますが、瀬川前会長ならびに前田景子前校長をはじめ関係各位のご尽力により「創立100周年記念事業」を立派に恙なく終えていただきましたことに感謝を申し上げるとともに、この100年という歴史を礎に次の一歩を踏み出し、世代を繋いでいく何かが出来ればと考えております。
この度の創立100周年記念事業の一環として編纂発刊された「奈良県立奈良高等学校百年史」にある“宝相華会(同窓会)の歩み”によると、『1929(昭和4)年3月2日、奈良中学校の第1回卒業証書授与式が挙行され、初代会長に初代校長古川正澄氏が就任し、卒業生代表に豊住謹一氏(1929年卒)が選ばれ「同窓会」が設立された。 1970(昭和45年4月)の総会を経て会長北河原公典氏のもと「宝相華会」と改称され、現在に至る。2025(令和7)年3月現在、奈良中学校・奈良市立奈良高等女学校・県立奈良高等学校(全日制・定時制・通信制・分校を含む)の卒業生を合わせた会員数は3万9974名になり、世代を超えた絆を育んでいる。会員相互の連携と親睦を深めてさらなる発展に寄与することを目的に、文化交流や支援活動など多岐にわたる事業を積極的に展開している。』とあります。
現在の宝相華会としての事業は、総会(4月)、支部総会(大阪7月・東京11月)、会報「宝相華」発行(9月,3月)、創立記念講演会(11月)、記念品贈呈式ならびに同窓会入会式(2月)、定時制同窓会「ともしび会」(4年に1度)、通信制同窓会「つどい会」(不定期)があり、現役生に対する支援として奈高教育推進基金に拠出し、「グローバル人材育成事業」「高大接続推進事業」の支援を行っています。
私は、1970(昭和45)年入-1973(昭和48)年卒で春日校舎から法蓮校舎への移転も済み、食堂やプールも完成した後でしたので、学校施設には不自由さを感じたことはなかったように思います。ただ、私はクラブ活動で卓球に入れ込んでいましたが、練習場は体育館の地下で柱の間々に卓球台があり、周囲は各クラブの部室に囲まれ、防音天井の隙間に球が入り込んで仕方なかったことだけは鮮明に覚えています。卓球以外にも色々と思い出はありますが、60歳の幹事年になった頃から同級生との集まりや卓球部のOB会などで顔を合わせる機会が増えて、各自がそれぞれに話す奈高時代の事柄や出来事で、改めて自分のことを思い出したり、友人を再認識したりするので、それが楽しみで出来るだけ参加するようにしています。大役を仰せつかった以上、このような機会も利用して宝相華会の事業への関心と関与をより一層深めてもらえるようにしていきたいと思っています。
会員の皆様には、総会や支部総会への参加や会報誌への寄稿、学年やクラスの同窓会、また所属クラブのOB・OG会の情報を宝相華会HPに提供していただくことなどにより、様々な業種や職種で活躍されている会員相互、縦横世代間での交流と親睦を深めていただき、併せて、現役生が未来に向かって勉学と諸活動に取り組んで行ける環境を提供し、社会で活躍し貢献してくれるための基になるようなご支援やご提案をお願いしたいと思います。
会員皆様のご理解とご協力をお願いするとともに、役員、理事の方々のご指導とお力添えをいただき、宝相華会としての役割を果たしていければと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。